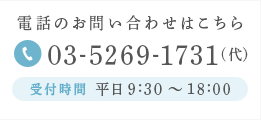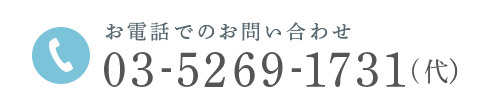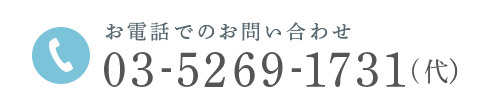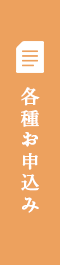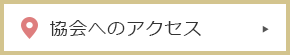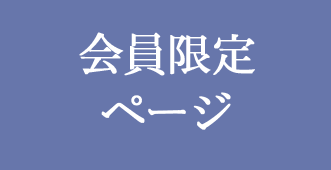室内でも予防医学を。
2020.04.09更新
新型コロナウイルス感染拡大の影響で不安定な時期が続いておりますが、皆様におかれましては体調等お変わりなくお過ごしでしょうか?
今週は緊急事態宣言が発令され、本部事務局のある東京都では外出自粛や3密回避、衛生面等に一層気を引き締め、人々の危機管理意識が高まっています。
当協会も感染拡大のリスクを抑制するため、時差出勤や在宅勤務を導入させて頂いております。
お問い合わせ対応やお手続きに通常よりお時間を頂き、ご迷惑をお掛けすることも多いかと思いますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
今回の影響で、外出機会が制限されている方が増えているかと思います。
仕事へ行けない方、休校等により自宅での生活をしばらく続けなくてはいけないお子さん、ご家族も多い状態です。
今現在は、ご自身、ご家族の安全はもちろん、できるだけ多くの国民の命を守るために、外出自粛や3密回避、手洗い・マスク・咳エチケット等の衛生対策を行っていくことが不可欠です。
しかし、自宅でテレビやインターネットだけの生活になってしまうと、運動不足やストレスにより免疫力が低下してしまう面がありますので、自宅での生活が多くなってしまった方は是非、以下のような対策を取り入れられているか確認してみて下さい。
1.朝、起床後は一杯の水を飲み、日光を浴びる
2.食事は1日3食、決まった時間に摂る
3.昼寝は20分までと決める
4.家事や階段の上り下りなどで身体を動かすよう心掛け、プラスで1日10分の運動(踏み台昇降、筋トレ、ストレッチ等)を行う
5.夜は日付が変わる前に就寝し、寝る1時間前にはテレビやスマートフォンの光を目に入れないようにする
6.笑いのある生活を
ポイントとしては自律神経の乱れを防ぐことと、血流・筋肉量を維持することです。
自律神経の乱れや血流の低下は免疫機能を低下させるとともに、脳の活動を低下させるので、感染リスクが上がったり、精神不安定や認知機能の低下を招く要因となります。
また水分摂取量が減ると血流が悪くなるので、1日1.5ℓ以上の水分摂取を心掛け、食事もバランスよく食べることで免疫機能を維持しましょう。(免疫細胞の材料も、脳・神経の材料も、ホルモンの材料も栄養です!)
「笑いのある生活」について、笑いはNK細胞の活性を高めたり、ストレスを軽減する効果がありますので、こんな時こそ、不安に陥り過ぎずに肩の力を抜き、笑いある時間を大切にしましょう。
何かと不安が多い時期ですが、皆様のご健康をお祈りするとともに、一日も早い収束を心より祈念申し上げます。
・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・
NPO法人 予防医学・代替医療振興協会
投稿者: