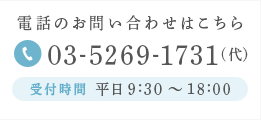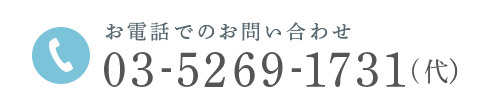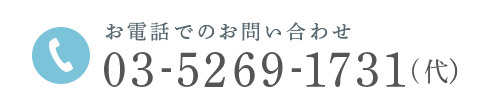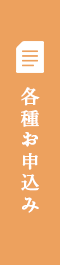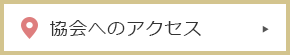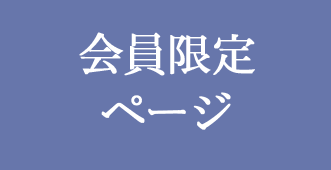引き続き、ザ・フナイ(2019年6月号)「本物の探究者」特集で紹介された岡治道先生の記事をご紹介させて頂きます。
・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…
■栄養学から栄養療法へ
1.栄養と栄養素
栄養(英:nutrition)とは、「生物が外界から物質を摂取し代謝してエネルギーを得、またこれを同化して成長すること。または、その摂取する物質」(出典:広辞苑)と定義され、栄養の源になる物質を栄養素(英:nutrient)といい、身体における役割や機能、更に健康との関係が解明されてきました。
明治以前には「栄養」と「営養」が同じ意味として用いられ、日本栄養学の開祖と称される佐伯矩(さいきただす)博士が1918年(大正7年)、文部省に建言し「栄養」の表記に統一されました。博士は1914年に世界初の栄養学専門研究機関を設立し、1924年に世界初の栄養士養成施設を開設し卒業生を「栄養士」と称しました。1934年(昭和9年)、世界に先駆けて日本栄養学会を設立し栄養学を医学から独立させ、1947年(昭和22年)には国立栄養研究所が設置され「栄養士法」が公布されました。このように、日本は栄養学の先進国として世界に貢献してきたのです。
栄養学とは、「生命の維持及び心身の健康を保つために、栄養の状態や必要度について研究する学問」や「栄養学は食品成分と生体との相互作用に関する科学」などと説明されています。
2.栄養療法とは
栄養学による科学的根拠をもとに、治療や養生、健康増進や身体機能の維持・亢進を目的に行われているのが現代の栄養療法です。栄養・生化学辞典には、栄養療法とは「栄養素の補給量を是正して治療効果の改善をはかる療法。絶食(断食)、飢餓や減食(栄養制限)など栄養素の摂取量を制限する方法。不足している栄養素を補充する方法。および例えば特定のビタミンなどを所要量以上に供給する方法などがある」と記されていますが、この中には高カロリー輸液・経腸栄養、疾病に合わせて特定栄養素や食材を付加あるいは除去した食事、メガビタミン療法、分子整合栄養医学理論に基づく栄養素の補充療法、断食療法などの様々な取り組みが含まれています。
従って栄養療法を行う場合には「何を目的とし」、「どの様な効果を期待して」、「いかなるアプローチを行うか」を、理論的背景を理解して選択する必要があります。
3.栄養学の発展と歴史
ここで人類と栄養の歴史を再確認しておきます。健康と食事の関係は古く、5千年以上前の古代メソポタミア時代の、健康状態に合わせた楔文字のレシピ集が残っています。古代エジプトではニンニク、胡麻、ヨーグルトなどを健康維持や強壮目的に使用し、紀元前200年頃の「神農本草経(しんのうほんぞうきょう)」には植物・動物・鉱物の人体に作用する効果の強さや使用法が記載されています。
そして栄養への科学的アプローチの始まりは、フランス革命前の1773年、アントワーヌ・ラヴォアジエ(近代科学の父、生理学の始祖)の呼吸の発見であるといわれています。1814年脂肪が発見され、1820年から1941年までに必須アミノ酸9種類が同定されました。1842年にユストゥス・リービッヒが糖、脂質、タンパク質を三大栄養素と命名しました。
栄養素がどの様に働くのかを研究したのがクロード・ベルナールで、1865年に出版された「実践医学序論」の中で、摂取された栄養素の一連の科学的変化を「代謝」と命名しました。このほかにも自律神経と糖代謝、消化吸収の機能、神経毒の作用などを解明し、「生理学・栄養学分野のモーツァルト」と呼ばれていますが、彼の「医学は科学的考察に基づかなくてはならない」と提言したことは、後の近代医学の礎となる提言で、医療に関わるものは常に教訓として心すべきものです。
さて、1912年にフレデリック・ホプキンスが三大栄養素のみでは生命の維持は不可能で、食品には未知の重要な微量栄養素が含まれているとし、これが後にビタミンと呼ばれます。当時死亡者の多かった脚気の撲滅に期待が寄せられ、ビタミンの研究に各国がしのぎを削っていました。本邦での脚気の被害は甚大で、「江戸わずらい」などとも呼ばれていましたが明治の陸海軍では脚気による死亡者が続出し、日露戦争(1904~1905年)では陸軍参戦総兵員約108万8000人、脚気患者は25万人に達し、戦病死者3万7200余人中脚気による死亡者2万7800余人(約75%)で多くは脚気死によるものだったとされています。戦死者数を脚気死数がしのぐこととなりました。
そして1906年に鈴木梅太郎教授(東京帝国大学農学部)が玄米から抗脚気物質のオリザリンを抽出し脚気の原因究明に成功しました。これが世界初のビタミン抽出(1936年にロバート・ウイリアムズよりVitB1と命名される)となりました。余談ですが、世界に誇るこの偉業は同じ大学の医学部の陰謀により、ノーベル賞の受賞が阻止されたことが、ノーベル財団の資料に残されています。
1906年に始まったビタミンの探求は1912年にビタミンA、1922年にE、D、1928年にCが発見され、その後B2、B6、B3(ナイアシン)、B9(葉酸)、B12、Kが1953年までに同定され、前述の脚気はビタミンB1、壊血病はC、ペラグラはナイアシン(B3)、クル病はD、巨赤芽球性貧血はB12の欠乏で発症することが明らかとなりました。
その後、必須アミノ酸を摂ることにより、食事からたんぱく質を摂取しなくても体内での働きを維持できることが証明され、現在では腸管切除後でも三大栄養素、ビタミン、ミネラル、微量元素の持続点滴(IVH)により、20年以上の生存が可能となっています。これは理想的な健康状態とは言えないながらも、救えなかった命を救命できたという観点から、栄養学は一つの大きな目的を達成したといえます。
その後も、海藻などに含まれる「ミネラル」、野菜や果物に含まれる「フィトケミカル」、「脂肪酸」においては生理活性や重要性が研究され、健康や老化、疾患との関係に関するおびただしい発見がなされています。更には腸内細菌の状態と腸の機能が、身体・精神・免疫機能に影響を及ぼすことが判明し「脳腸相関」と言われるネットワークの存在が注目されています。これは栄養素やエネルギー代謝を超えた、生命内部のネットワークと生物活性物質の関係性という新たな研究分野の幕開けとなっています。
・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…
▶続きは、岡治道医師、掲載記事のご紹介④「細胞膜栄養療法と背景」へ