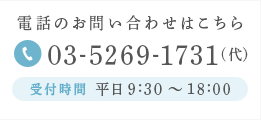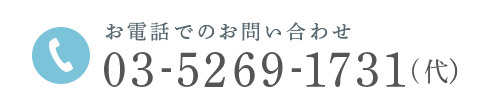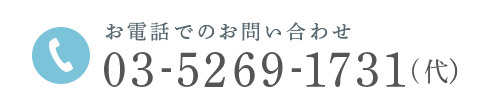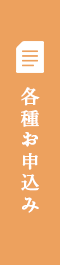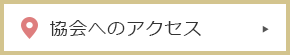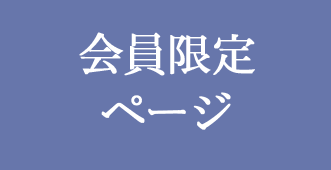昨年よりマイクロプラスチックの問題をよく耳にするようになりました。
プラスチックゴミによる環境汚染や自然動物への影響は長年、課題とされていましたが、マイクロプラスチックは自然へ流出しているプラスチックが目に見えないほど細かい粒子となり、食物連鎖で私たちの口の中に入ってくることが懸念されています。
実際、WWF(世界自然保護基金)が2019年6月に発表した研究によると、飲料水や魚介類などの食事経由から摂取するプラスチックは、1週間当たり重量換算で5グラムに相当するとされています。
1週間でプラスチック5グラムというと…
◇クレジットカード1枚
◇1日あたりストロー1本分(約0.7グラム)
マイクロプラスチックとは、環境中に存在する5ミリメートル未満のプラスチックと定義されていますが、実際にはマイクロメートル、ナノメートル単位の目で見えない大きさのものも多く存在しています。
海に流出するプラスチックゴミが年月をかけ漂流することでプラスチック片が細かくなり、それをプランクトンが溜め込み、プランクトンを小魚が食べ、小魚を大型の魚が食べ、大型の魚に濃縮されていくことなどが示されています。
これらのマイクロプラスチックは果たして体内に吸収されるのでしょうか?
欧州食品安全機関(EFSA)は、サイズによって吸収される度合が異なることを指摘しています。
150マイクロメートル未満では体内の消化管から吸収される可能性が出てきて、1.5マイクロメートル未満では体内の各組織に深く浸透する可能性が出てくるとされています。
飲料の場合、カナダの研究では水道水よりもペットボトルの水の方がプラスチックが多く検出され、ドイツの研究では更に再利用(リユース)のペットボトルからは新品ペットボトルの3倍以上のプラスチックが検出されたそうです。
また、食品についての評価では、検出データのある食品群だけのデータを使った分析なので、過小評価の可能性が大きいとされていて、肉類や穀物、野菜などはデータがないため、対象とされていません。
例えばEFSAの報告では、マイクロプラスチックを含んだ魚粉が鶏や豚の餌に使われている場合、肉に残っている可能性を指摘していますが、そうしたデータはまだ存在しません。
カナダの論文の筆頭著者であるキエラン・コックス博士は、論文の中で「マイクロプラスチックの暴露を減らす有効な方向はペットボトルの水を避けること。今後肉や野菜、穀類などの汚染データの研究も必須であるが、予防原則を適用とすれば、人間の暴露を減らすための最も有効な方法は、プラスチックの生産と利用を減らすことだ」と結論づけています。
人体への影響についてはまだ明確になっていませんが、本来、人体に入ってくるべきでない化合物が入れば、腸管免疫の低下や、神経障害など、様々な影響に繋がる可能性があります。
予防医学としてはもちろん、環境のため、私たちの子孫のためにも、プラスチック問題を今一度見直してみることは大切なのではありませんでしょうか。
参考・一部転載:WWFジャパン「海洋プラスチック問題について」/オルター通信No.1630/食の安全ウォッチNo.63

・‥…━…‥・‥…━…‥・‥…━…‥・
NPO法人 予防医学・代替医療振興協会