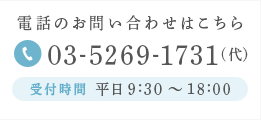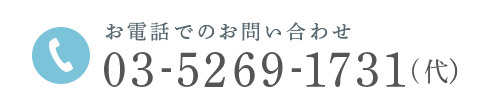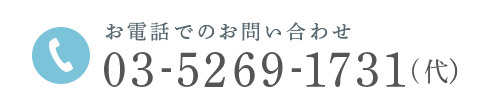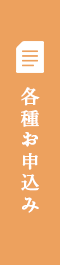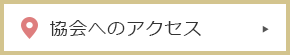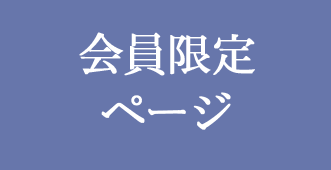国が定める食事摂取基準
2025.11.10更新
私達が栄養素を摂取するのは、前述の身体の材料が理想的に揃うようにするためです。現在その目安量は、厚生労働省から食事摂取基準として算出されています。
日本人が健康を維持し、病気を予防するために、1日に必要とされる栄養素の量を示した国の指標です。
厚生労働省が5年ごとに見直しており、ビタミン・ミネラル・たんぱく質・脂質などの栄養素ごとに、年齢や性別、身体活動量に応じた目安が定められています。
1. 推定平均必要量(EAR:Estimated Average Requirement)
その栄養素を必要とする人の半分(50%)が満たせる量
この量より下回ると、不足している可能性が高いとされ、主に集団の栄養状態を評価する際に使われる
2. 推奨量(RDA:Recommended Dietary Allowance)
EARに基づいて、「ほとんどの人(97〜98%)が必要量を満たす」とされる量
健康を維持するために、個人が目安とするのに適した数値
3. 目安量(AI:Adequate Intake)
科学的な根拠が不十分でEARやRDAを設定できないときに、観察や実績から導かれた“とりあえずこのくらい”の量
特に、水分や食物繊維、ビオチンなどの栄養素に使われることが多い
4. 耐容上限量(UL:Tolerable Upper Intake Level)
これ以上とると健康に害が出る可能性がある上限値
サプリメントなどを利用する人は、とくにこの数値を超えないよう注意が必要
5. 目標量(DG:Dietary Goal)
生活習慣病の予防を目的として、設定された数値
主に脂質、ナトリウム(塩分)、炭水化物などに設定されている
ただし、ここで気をつけたいのは、この基準は“平均的な日本人”のための、最低限のガイドラインであるということです。たとえば、ストレスが多い人はビタミンCをたくさん消耗しますし、加工食品が多い人はマグネシウムや亜鉛が不足しがちです。こうした個人差やライフスタイルの違い・ストレス環境までは、基準の中には織り込まれていないのが現実です。つまり、健康な人が「病気にならないため」の基準であって、不調を改善したり、ベストな状態をめざしたりするには足りないこともあるのです。
投稿者: